相続による事業承継

こんにちは。
愛知県豊川市の行政書士おおいし法務事務所の大石法良です。私が以前勤めていた会社で、私の直接の上司であり、師匠でもあった社長が突然倒れ、亡くなったことがありました。経営者は、突然そうなった場合のことも頭に入れ、準備をしなければなりません。
避けて通れない「事業承継」
経営者にとっては、「自分個人の資産」に加え、「会社の株式」や「自社ビル、工場」、「事業用の土地」、「工場などで使う機械」など、次世代に承継しなければならない資産があります。
会社を承継する者、上記のような色々な財産の行先などは公証人役場で作成する「公正証書遺言」を用いて、自分の意思表示ができる年齢、かつ認知症などを認められない健勝なうちに作成しておけば、遺言公正証書として公証役場に原本が保存されますので、後から不正な改ざんが行われるようなこともありません。会社の経営は自分だけでなく、従業員の皆さんや取引先をも巻き込む問題となります。まだ早いのではないか?と思うくらいの時期から準備を始めていくことが大切です。
会社または個人の現状把握
事業承継を考えるにあたって最初にするべきことは、事業主体(会社など)の現状を正しく把握することです。財務状況など、会社の経営状態や事業に関係する市場の動向、そして資産、負債、会社の関係者と取引先などを整理することも大切です。株主の構成も再確認しておきましょう。これは、実際に経営に携わっていない株主が事業承継後、経営にどの程度関わってくる可能性があるか?という予測をする上でのポイントになります。行っている事業が、今後どのように、どの程度発展していけるかを考えるために、従業員の人数や年齢構成も把握しておきましょう。また、経営者自身の株式保有比率は、事業承継をスムーズに行う上で鍵になります。経営者個人の資産や負債もできる限り明確にしておくことが重要です。なぜなら資産の状況次第で、相続税対策や納税資金の準備が必要になることもあり、そうした事態を想定して準備を進めましょう。
事業承継の方法と経営計画の立案
実際に誰が事業を引き継ぐか、つまり後継者を選定し、指名することは会社の運命を決める最重要な項目ともいえるものです。後継者候補となる人をリストアップし、それぞれの候補を実際に後継者にした場合のメリットやデメリットやその本人たちの意思確認を経て、決める必要があります。依然として日本では約半数の中小企業が親族内での事業承継を行っています。事業承継方法が決まったら、おおむね3年から5年の中長期にわたる経営計画を立てます。現在の経営者から後継者となる人に、自分の経営理念や行動指針など後継者に承継させたいことをしっかり伝えることが大切です。具体的なビジョンの中で将来の数値目標を定め、経営計画書を作成し、と同時に資金繰りのことも考えておきたいところです。
親族内で承継する際の注意点
後継者候補となる人が複数いる場合には承継した人と他の親族との間で相続後に関係が悪化することもありますので、承継を行う前から、親族の理解を求める働きかけをすることも必要になります。そして、経営を安定させるためには誰がどのくらい株式を持っているかという株式の保有比率も重要です。後継者となる人とその人に友好的だと思われる株主に、株式を集中させておくとスムーズに事業承継が行えるのではないでしょうか(株主総会で重要事項を決議できる総株主の3分の2以上の議決権を確保しておく。)。
ただ、株式の集中にあたっては、「遺留分」が障壁になることがあります。遺留分というのは、兄弟姉妹以外の法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)につき、これだけは保障するとされている遺産の割合のことです。
このように、事業承継する上では、考えておくべきポイントが非常に多いため、出来るだけ早い時期から法律家などの専門家と綿密に打ち合わせをしながら長期計画で進めていくことが大切です。
愛知で相続に関連する業務・遺言書の作成サポートをご希望なら【行政書士おおいし法務事務所】まで
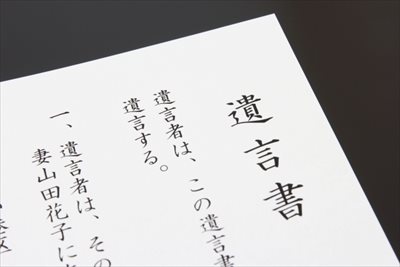
愛知で相続に関連する業務手続き・遺言書の作成サポートをご希望の方は、【行政書士おおいし法務事務所】へお任せください。
ご自分の死後、家族の安心・団結を願うなら、遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の作成をおすすめします。また、ご家族がお亡くなりになり相続手続きが必要になった場合、他士業と連携し、遺産分割手続きを代行いたします。
TEL:0533-95-2002 ※お電話でのお問い合わせは随時受け付けております。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




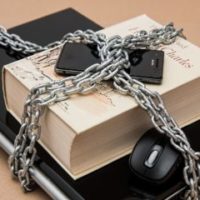




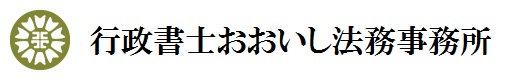
この記事へのコメントはありません。